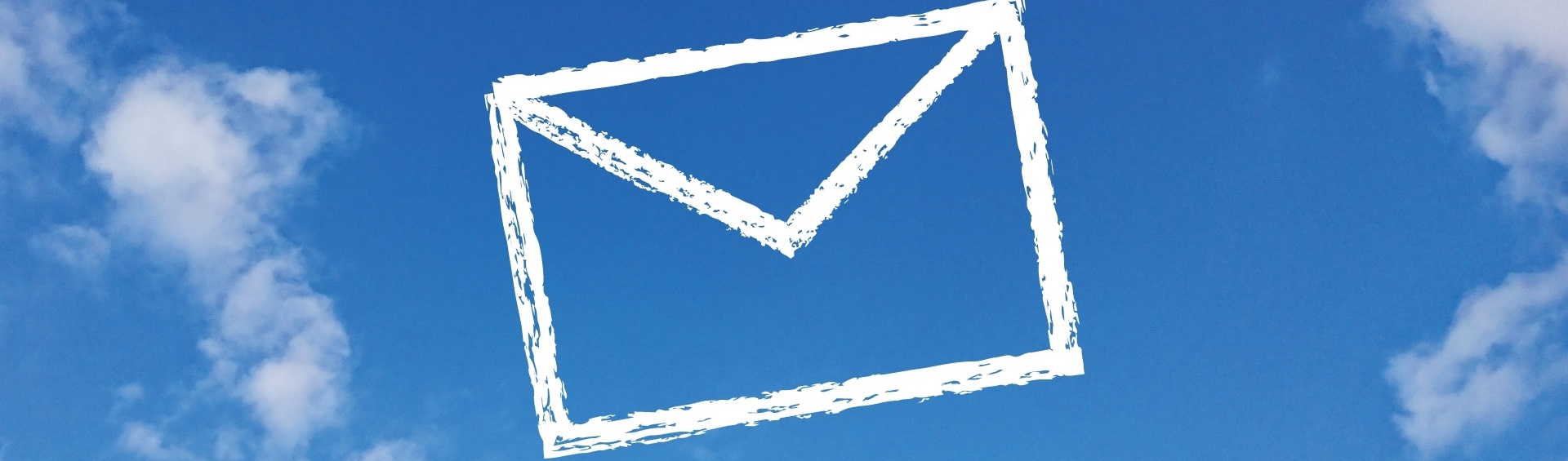ここでは、山岳会会員が日和田山での自主的なクライミング練習中に転落、負傷した事故の裁判をとおして、山岳会の登山事故における、指導的立場にあった会員の法的責任について検討を加えてみます。
目次
日和田山転落(クライミング)事故の概要
パーティー登山での遭難事故として(c)山岳会での登山事故をみてみます。
下記の記事で若干触れましたⅵ)日和田山でのロッククライミング練習中の新人会員転落受傷事故(以下、「日和田山転落事故」といいます。尚、「日和田山クライミング事故」ともいわれています。)の判決について、詳細にみてみます。
この事故は、山岳会入会6か月目のロッククライミングの練習経験のない会員(以下「甲」といいます。)が、クライミング経験豊富(詳細はわかりませんが、判決では「三大岩場と称される岩場を踏破するなど、山登りの経験が豊か」と認定されています。)な同じ山岳会の会員(以下「乙」といいます。)との日和田山でのクライミング練習中、転落したものです。
事故当時、乙が甲をビレイしていました。
この事故の後、甲は乙に対し、不法行為に基づく損害賠償を求め、提訴しました。
尚、裁判の認定によると、事故当日の練習は、山岳会が会として主催したものではなく、面識のあった会員同士の自主的な練習であったようです。
日和田山転落事故の判決内容
事故の発生状況に関する認定について
この事故の起きた状況を、裁判所は次のように認定しています。
高さ約七メートルの本件露岩で足慣らしをすることにし・・・原告にザイルの結び方と三点確保の要領を教え、原告にヘルメットとゼルプストを貸し与え、ザイルを自己と原告のゼルプストに結び、単独で登攀を開始し・・・途中で高さ2.8メートルの位置に奥行き約三〇センチメートルの本件足場のあることを確認し、頂上付近まで登り、腰を降ろして、そこに打たれていた二本のボルトにシュリンゲを通して自己の身体を確保し・・・腰がらみの方法で確保体勢をとり・・・原告が登ってくるにつれザイルを手繰りよせ、手繰りよせたザイルを腰の後ろに回して、ザイルを弛みのない張った状態にしていた。本件露岩は、ホールド付近が被り気味になっており、本件足場の高さは約2.8メートルしかな(かったが、)・・・被告は・・・原告に登攀の途中で両手を離させ、ザイルで原告の身体を確保するための事前の打合せをせず、原告にどのような確保体勢をとり手を離せばよいのかについての説明はしなかった。原告が、本件足場に立ったとき、被告は、原告に足場が大丈夫か尋ね、原告が大丈夫と答えたため、「手を離してごらん。」と言った。原告は・・・手を離すとザイルで確保していなければ落ちてしまうおそれがあり、また、登攀の途中で手を離す練習をするなどとは事前に説明もなかったので、意外に思い「冗談でしょう。」と言ったが、一瞬手を離し岩にしがみついた。ところが、被告は、「ロープで確保しているから、もう一回手を離してごらん。」と言ったので、原告は、被告がそこまで言うのなら大丈夫だと思って、手を離した・・・が、次の瞬間、原告は、仰向けに頭から転落し、被告がザイルを握り締め制動したが間に合わず、第七頚椎を骨折し頚髄損傷の障害を負った
横浜地判平成3年1月21日
過失の認定
このような状況において、裁判所は乙に対し、次のような注意義務を認定しています。
被告は原告に岩登りの技術を教示する立場にあり、原告は岩のぼりの初心者であったのであるから、被告は、原告に登攀の途中で両手を離させザイルと原告の足で身体の確保をする練習をするときは、まず、転落事故のないような場所を選択し、原告に事前にどのような確保体勢をとり手を離せばよいかを十分に説明し、手を離させる瞬間において、ザイルの確保をはかるタイミングがずれないように掛声をかけるなど転落事故が起こらないような措置を講ずるべきである。そして、転落事故が発生する場合に備えて、ザイルの確保を十分にしておく注意義務がある
横浜地判平成3年1月21日
また、乙の予見義務として、
本件露岩で両手を離す練習をする場合には原告が転落しザイルに一気に加重がかかることまで予見すべきであり
横浜地判平成3年1月21日
としています。
その上で、
被告には・・・高度の注意義務があるにもかかわらず、漫然・・・練習をした点に過失があるものと認めざるを得ない
横浜地判平成3年1月21日
として、乙は、上記の注意義務に反しており、過失が認定できるとしています。
これにより、裁判所は、甲の乙に対する、不法行為に基づく損害賠償請求を認容しています。
過失相殺について
裁判における乙の主張
尚、この裁判では、甲の落ち度について、乙が次のような主張をしています。
そもそも登山は、生命身体の危険性が高い野外活動であり、成人になって登山を行う者は、その危険性を十分知ったうえで行動すべきである。また、一緒に登山を行う者は、お互いの行動いかんによっては、双方の生命身体に危険の発生するおそれがあるのであるから、お互いに信頼しあい、かつ、お互いに自らの生命身体の危険を防止するように努めるべき義務があるというべきである。さらに、登山の中でも、岩登りは特に危険であるから、岩登りの練習を自ら希望し被告を誘った原告自身も、岩登りに対する知識を十分に習得し、その危険防止のために十分注意を払うべきであり、そのための努力を尽くすべきであった
横浜地判平成3年1月21日
過失相殺に関する裁判所の判断
裁判所は、この乙の主張に対し、次のように判示し、3割の過失相殺をしています。
原告は、岩登りは初心者であったとはいえ、岩登りは、パーティーを組む者同志の相互協力を要する生命身体に危険のあるスポーツであるのであるから、自己の身体の安全確保については、自らも十分に注意すべきであり、原告としてもどのような確保体勢をとり手を離せばよいか被告に説明を求めるべきであったのにこれを怠り、漫然被告の言うがままに手を離した点について落ち度があるといわざるをえない
横浜地判平成3年1月21日
上記の乙の主張は、下記の記事でご紹介しましたo)涸沢岳滑落事故の判決において、
大学生の課外活動としての登山において,これに参加する者は,その年齢に照らすと・・・原則として,自らの責任において・・・計画を策定し,必要な装備の決定及び事前訓練の実施等をし・・・危険を回避する措置を講じるべきものといわなければならない。
名古屋高判平成15年3月12日
・・・大学生の課外活動としての登山におけるパーティーのリーダーは,そのメンバーに対し・・・事故の発生が具体的に予見できる場合は格別,そうでなければ,原則として・・・メンバーの安全を確保すべき法律上の注意義務を負うものではなく,例外的に,メンバーが初心者等であって,その自律的判断を期待することができないような者である場合に限って,上記の事柄についてメンバーの安全を確保すべき法律上の注意義務を負う
と裁判所が判示しているのと親和性が高いものと考えられます。
乙の注意義務と過失責任について
上記の涸沢岳滑落事故の判決引用部分では、大学のサークルにおいても、原則として、メンバーは自己責任において、危険を回避する措置をとるものとされています。
同判決の趣旨からしますと、大学のサークル以上に、入会に際して会員の自由意志が尊重される山岳会においては、原則として、成人会員を構成員とするパーティーのリーダーは、他の会員メンバーの安全を確保すべき法律上の注意義務を負わないものと考えられます。
注意義務が認められるのは例外的な場合に限定されていると思われます。
甲は事故当時30歳代であったことから、o)涸沢岳滑落事故で死亡した大学生以上に判断能力を有する者と言え、乙に注意義務が認められなくともおかしくないように思われます。
しかし、o)涸沢岳滑落事故とⅵ)日和田山転落事故とでは、前者は雪山のパーティー登山ではありますが、ザイルを出しておらず、事故当時、各々が距離をとり下山していたのに対し、後者ではザイルを出しており、一体として行動していたという違いがあります。
また、ⅵ)日和田山転落事故では、クライミングの練習経験すらない者を経験豊富な会員が指導していたのですから、これまでにみてきた事故の中では、むしろ、参加者に冬山未経験者まで含まれていたⅴ)大日岳遭難事故(下記の記事で紹介しています。)に近いものともいえます。
そして、初心者のクライミングの練習という性質上、事故の発生の可能性を認識できたと思われることから、上記で引用したo)涸沢岳滑落事故2つ目の引用箇所の前半の例外部分に該当、あるいは後半に該当するものと考えられます。
このような事情もあり、ⅵ)日和田山転落事故の判決では、甲が成人でありながら、乙に対し重い注意義務が認定されたものと考えられます。
乙の落ち度と過失相殺について
しかし、ⅵ)日和田山転落事故判決では、過失相殺を認め、甲にも一定の範囲で落ち度を認めています。
この点、風に飛ばされた帽子を取ろうとして滑落したⅲ)石鎚山転落事故の判決(下記の記事で紹介しています。)において、
教諭が最終的には原告に許可を与え・・・その許可に従った原告に過失相殺すべきほどの落ち度があったとすることもできない
松山地裁今治支部判決平成元年6月27日
として、未成年である中学生の落ち度を否定しているのとは異なります。
しかし、ふたつの事故を、客観的な行為面からみますと、帽子を取りに崖に降りたⅲ)石鎚山転落事故の被害者側の「落ち度」らしさの方が、ビレーして貰いながらクライミングの練習の一環として両手を岩から離したⅵ)日和田山転落事故の被害者の「落ち度」らしさより大きいようにも思われます。
それでは、2つの事故において、過失相殺の認定が何故異なっているのでしょうか。
まず、上記で述べました過失相殺とは、民事上の損害賠償請求において、被害者側にも落ち度がある場合に、賠償額を減額するものです。
このように、過失相殺とは、民事上の損害額に関係する法的な概念です。
同じ民事上の問題としては、ⅲ)石鎚山転落事故では、被害者は中学生であり、中学生には責任能力が認められないようにも思われます(民法712条参照)。
そうすると、被害者の責任能力の問題から、ⅲ)石鎚山転落事故においては、被害者の落ち度の有無とは関係なく、過失相殺は、元々問題となり得なかったとも考えられます。
しかし、責任能力は11~12歳くらいから認められるとする裁判例も多く、また過失相殺の認定に要求されるのは、一般的に「過失相殺能力」といわれている能力であり、責任能力とは別のものです。
そして、この過失相殺能力が認められるためには、最高裁の判例からも、責任能力までは要求されず、「事理弁識能力」があればよいとされており、多くの裁判例では、事理弁識能力は小学校入学前後の年齢から備えるとしています。
このことから、中学生に過失相殺能力を認めることは問題なく、被害者の落ち度によっては、中学生が被害者の場合でも過失相殺をなし得ると考えられます。
そうしますと、やはり、
- ⅴ)日和田山転落事故が、大日岳遭難事故に近い事例といえども、教育活動における教員の注意義務と、山岳会の乙の注意義務とでは性質が異なると考えられること
- 成人と中学生では判断能力に大きな差があること
等から、ⅵ)日和田山転落事故とⅲ)石鎚山転落事故の判決における、負傷者の落ち度らしさの認定の違いが生じたものと考えられます。
山岳会での登山事故におけるリーダーの法的責任について
ここで紹介しました他の裁判の判決との比較からしましても、成人の山岳会会員のパーティー登山での事故においては、一般的には、リーダーに他のメンバーへの注意義務は認められないと考えられます。
しかし、登山技術の訓練など、一定の場合においては、指導的立場にある会員が他の会員に対し注意義務を負うこともあります。
ただし、成人である山岳会会員の登山事故においては、初心者のクライミング練習のように教育的側面が強い活動時の事故においても、指導的立場にある会員の責任は、教育活動の登山における教員の責任とは程度が異なります。
また、仮に指導的立場にある会員に損害賠償責任が認められる場合においても、傷害などの被害を負った会員に一定の落ち度が認められ、過失相殺により損害賠償額が減額されることがあり得ます。