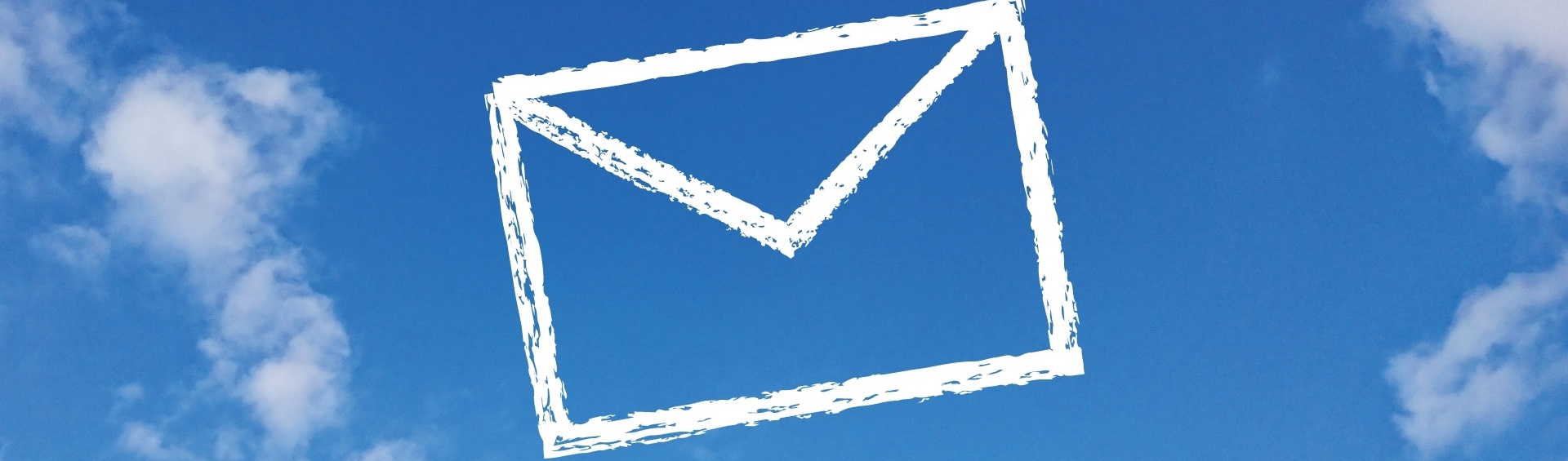目次
富士山ヘリコプター事故の概要
今回は、遭難者救助時の事故として12)富士山ヘリコプター事故をみてみます。
この事故の遭難者(以下「A」といいます。)は、11月末から12月初頭に6名のパーティーで富士山登山をおこないましたが、8合目で体調不良者2名が下山、その後4名で山頂を目指しました。
しかし、午前11時ころ標高約3600mの9.5合目で天候不良等のため登頂を断念、4名でアンザイレンしながら下山していたところ、午前11時10分ころ1名が滑落し、Aを含む他の3名もこれに引き込まれ約250m、標高約3469mの地点まで斜面を滑落しました。
その後、Aの救助活動を午後4時2分から開始した3名の救助隊員(ヘリコプター機長(以下「乙」といいます。)、活動指揮者兼オペレーター(以下「丙」といいます。)および救助員(以下「丁」といいます。))が搭乗した消防航空隊のヘリコプターが遭難現場に到着し、吊上げ用救助器具のデラックス・サバイバー・スリング(以下「DSV」といいます。)をAに装着してヘリコプター機内へ収容しようとしました。
しかし、ヘリコプターの高さまでAを吊り上げることは出来たものの、機内にAをうまく引き込めず、引込み動作を繰り返すうちにAの身体がDSVから抜け、落ちそうになったため、ヘリコプターを下降させました。
しかし、午後4時13分ころ、Aは地上数mの高さから落下してしまいました。
このため、午後4時14分ころ再度丁が地表に降り、AにDSVを装着しようと試みているうちに、気流の影響でヘリコプターのホバリングが維持できなくなり、同日の救助を断念することとなり、ヘリコプターは帰還しました。
翌日午前9時ころ、警察地上隊によりAは発見・収容されたのですが、胸部および頭部損傷兼寒冷死により既に死亡していました。
Aの遺族は、消防航空隊の救助活動に過失があったとして、消防航空隊が所属する地方公共団体(以下「甲」といいます。)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め提訴しましたが、1審では、消防航空隊の救助活動の過失は否定され、原告の請求は棄却されました。
消防航空隊の事情
この事故では、Aらが滑落した午前11時10分ころの直後、11時14分に110番通報がありました。
これを受けて出動した県警航空隊のヘリコプターは午後0時30分に現場に到着、上空から遭難者を確認しました。
しかし、現場上空の気流の悪化と燃料補給のため一度現場を離れ、再度午後3時28分に現場に戻り、午後4時1分にAとは別の負傷者を機内に収容しました。
一方、消防航空隊は、午前11時30分に本件事故の発生と出動要請の可能性がある旨の情報提供を受けていました。
しかし、正式の救助出動要請を受けたのが午後3時14分であったことから、夕刻に救助隊員を現場に派遣することとなりました。
日没時刻が迫っていたこと、および現場付近の状況などから、救助員のホイストカット無しで救助活動することを出動前に決定し、ヘリコプターから不要な救助器具などを降ろし荷重を軽くして午後3時29分にヘリポートを離陸しました。
しかし、午後3時45分に滑落現場付近の上空に到着したものの、更に現場で県警航空隊の救助活動が終了するのを待って救助活動をはじめざるを得ませんでした。
裁判所の判断
原告の主張した消防航空隊の過失
この事故の裁判では、原告らは、消防航空隊の救助活動に、
①救助器具の選択を誤った過失
②救助器具の使用方法を誤った過失
③収容の際支障となる事態の確認を怠った等の過失
④適切な再救助をしなかった過失
⑤落下位置情報を適切に県警察地上隊に伝達しなかった過失
があると主張しました。
裁判所の過失に関する判断
上記の原告の主張に対し、裁判所は消防航空隊の過失に関し、次のように判示しています。
まず、国家賠償法上の違法性の判断に関し、
・・・山岳遭難者にあっては・・・早急に救助活動を実施する必要があるが,山岳遭難者に係る救助方法を決定するに当たっては・・・救助隊員の人数・身体状態・携行する装備・応援の有無及び二次遭難に遭うおそれといった種々の事情を考慮しなければならず,かつ,これらの事情のうちには刻一刻変化するものがあるから・・・適切な救助方法の選択に当たっては,実際に救助に当たる救助隊員の合理的な判断に委ねるのが相当で・・・本件のような極めて高高度における山岳救助においては,救助現場の外気温・気圧が低く,また高高度への急上昇が必要となるから,これら外的要因が,救助隊員の身体能力や,思考・判断能力に大きな影響を及ぼす可能性は否定できない・・・(ので)救助時の救助隊員及び要救助者が置かれた具体的状況に照らし,救助隊員が,救助に際して明らかに合理的と認められない方法をとった場合は,職務上の注意義務を欠いた違法なものとなるが,そうでない場合は,救助方法の選択等は救助隊員の合理的裁量に属し,違法とならないと解すべき
京都地判平成29年12月7日
として、下記の記事で解説しています、同じく山岳救助時の救助者の過失が問題となった、11)積丹岳遭難事故の判決と同じ判断枠組みを採用しています。
その上で、①救助器具の選択に関しては、
被告救助隊員がDの救助を開始したのは午後4時2分であり,日没まで30分程度の時間しかなかった。エバックハーネスはヘリコプターのダウンウォッシュ下では装着が困難であるため,いったんホイストカットして,丁を現場に残して離れる必要があるが,被告救助隊員によるAの救助活動の際,不意の乱気流が生じる可能性があり,そうなるとヘリコプターは現場に戻られず,要救助者はもとよりビバークの技術を持たない丁も二次遭難に至るおそれがあった。また,ピタゴールについても,ダウンウォッシュの影響を強く受ける上,展開したピタゴール底辺部に要救助者を膝を立たせて着座させて装着しなければならず・・・,負傷したAに用いるには不適当であった。以上の事情の下では,本件救助活動当時エバックハーネスやピタゴール等の救助器具を使用すべき義務が被告救助隊員にあったということはできない。被告救助隊員が,ホイストカット無しでダウンウォッシュ下でも迅速な救助が可能な救助器具(DSV)を選択したことに過失はない
京都地判平成29年12月7日
としています。
ここでは、具体的状況下の制約の中で、一定の合理性を有する救助器具の選択をしていたとして、過失を否定しています。
また、②救助器具の使用方法に関しては、
Aに装着されたDSVの胸バンドの締付けが弱かったことを推認させる的確な証拠はない・・・DSVについて,股下シートを使用しない場合には,通常程度の強さで胸バンドを縛着したとしても,要救助者からDSVが外れることがあるのであって,本件でAからDSVが外れたことをもって,丁がしたAのDSV胸バンドの締付けが甘かったということはできない。
・・・丁は,Aの胸付近にあったフリースウェアを保持し,丙に手渡したにすぎず,これによってAのDSV胸バンドの縛着が緩まったというのは証拠を伴わない推測にすぎない。丁のAへの胸バンドの締付け方法に過失があったと認めるに足りる証拠はない。
・・・要救助者がDSVから抜けないようにするには,要救助者が両脇を締めることが重要なのであって,取っ手をつかむことは単に要救助者がカラビナ等に指を挟まないようにするための措置にすぎない・・・救助員は,DSV使用に際し,要救助者が自分で脇を締められることを確認する必要があるが,両手で取っ手をつかませる注意義務があるわけではない。本件で,Aが自分で脇を締めることができたことは,実際にAを現場から吊り上げることができたこと,被告救助隊員がヘリコプターにAを収容する動作を開始するまでAがその姿勢を保持していたと認められることから明らかである。
・・・股下シートについて,Dが当時体力を消耗した状態にあったことを踏まえると,Gとしては,Dの落下を防ぐためには股下シートを装着することがより適切であったということができる(が、)・・・Aの救助開始時点ですでに日没まであまり時間がな(く)・・・低い位置でヘリコプターのホバリングを継続すること自体が・・・危険を伴うもので・・・いつ乱気流,突風に見舞われ,機体が安定を保てなくなるのか全く見通しのない中で,一刻を争う救助活動が要求されたのである。現に・・・県警航空隊のヘリコプターは午後0時30分に現場に至ったが気流の悪化等のため現場に進入することができず・・・を収容し現場を去る際,被告救助隊員に気流につき注意を喚起した。さらに,被告救助隊員の再度の救助の際,乱気流の中,ヘリコプターは,安定を保つことができず,乙は地上に降りた丁にホイストカットを指示し,同人を残して一時現場離脱するという決断までした。最初の救助時,再度の救助の際に乙が認識したような機体の不安定が生じたことを認めるに足りる証拠はない。しかし,それは回顧的にいえることであって,最初の救助時に,被告救助隊員が向後数分ないし十数分間風が安定していると予測し得たわけではない
・・・Aのブリザードパックは,足部から腹部まで施されており,仰臥位で自ら動くことができず膝を曲げた状態にあるDについて,ダウンウォッシュの影響下において丁一人で短時間のうちに取り外すことは困難であったと推認することができる
・・・股下シート自体は補助的なものとされ,必ず使用すべきものとされるわけではない救助器具であり・・・股下シートを通さなければ,要救助者を吊り上げることができず,容易に要救助者を落下させてしまうような器具ではない・・・
ヘリコプターの安定を保つことが困難な当時の状況下で,Gは,股下シートの装着に時間をかけるより,意識のある状態のDをDSVで一刻も早く吊り上げ,現場を離脱することを優先し,それがDの状態から可能であると判断したものであり,現に吊上げ自体は成功したことからすると,Gの判断は,前記気象状況下,要救助者の心身の状態に照らすと救助員としての合理的な裁量の範囲であったと認めることができ・・・股下シートを装着させなかったことにつき,過失があったと認めることはできない
京都地判平成29年12月7日
と原告が過失を主張した行為ごとに過失の検討をおこなっています。
本件では、日没迫る過酷な環境下の救助でもあり、救助者の判断の裁量は広く解されています。
そこで、安全性を一定程度犠牲にしても、救助活動に要する時間を短縮することを優先せざるを得ない状況であったとする救助員の判断についても、一定の合理性が認められる以上(仮にベストの選択ではなかったとしても)、過失の成立は否定されることとなります。
ここでは、救助時間短縮との関係もあり、股下シートを使用しなかったことについても、「救助員としての合理的な裁量の範囲であった」とされ、過失の存在が否定されています。
次に③収容の際支障となる事態の確認に関し、
最初の救助時,ヘリコプターへの収容の際,Dの足背部がスキッドに引っかかっていたものであり,丙が,DSVの取っ手を引っ張ってAを引き込もうとした直後,Aの体はDSVから抜けるようにして落下し始めた。しかし,Aの下半身は,ブリザードパックで覆われており・・・スキッドより上まで吊り上げた後のAの足元はダウンウォッシュの影響も受けていたと考えられるから,丙及び丁が,Aの足元を視認して,同人の足の位置及び状況を確認することは極めて困難で・・・丙の位置,丁がAと同じフックにつながっていたこと,収容動作を開始してからAがDSVから抜けるまで約10秒にすぎなかったこと・・・からすると,収容の際,Aの足をスキッドから外して,引き込むべきであったということはできない
京都地判平成29年12月7日
と過失を否定しています。
④適切な再救助をしなかったという点については、
再救助の際においても,・・・状況に・・・変わりはなく・・・救助隊員が,Aの再救助において,救助器具にDSVを選択したことには合理性が認められ・・・丁は,訓練以外でオペレーターを担当したことがなく,冬の富士山頂での救助も初めての経験であったから・・・機体の安全等を確認すべきオペレーターの役割を担うことは困難であったと認められ・・・丁と丙が役割を交代すべきであったということはできない
京都地判平成29年12月7日
と判示して過失を否定しています。
ここでは、救助隊員の具体的な経験、スキルも考え併せ過失の有無について検討を加えています。
更に、⑤落下位置情報を適切に県警察地上隊に伝達しなかったという点については、
消防航空隊は,落下現場の位置を県警航空隊に伝えたのであって,・・・市消防航空隊に,さらに・・・県警察地上隊に落下場所を伝えるべき義務があったとはいえない
京都地判平成29年12月7日
として、県警に落下場所を伝える義務はないとして、過失を否定しています。
救助者の注意義務について
12)富士山ヘリコプター事故は、独立峰である富士山の3500m付近での冬季の日没間近という過酷な条件下での遭難救助において発生した事故であることから、救助者に要求された注意義務の水準は相当低いものであったと考えられます。
その注意義務の水準を前提に、この判決は下されているといえます。
上記の②救助器具の使用方法に関する裁判所の判断箇所に、「・・・乙が認識したような機体の不安定が生じたことを認めるに足りる証拠はない。しかし,それは回顧的にいえることであって,最初の救助時に・・・予測し得たわけではない」とあるように、過失責任は注意義務違反であり、結果責任ではありません。
そして、事後的に掌握できる客観的事実ではなく、問題とされる行為がなされた時点で救助者が認識し、あるいは認識し得た事情を基礎として、注意義務違反があったか否かを判断することとなります。
また、上記の国家賠償法上の違法性判断の枠組みに関する判示箇所において、「外的要因が,救助隊員の身体能力や,思考・判断能力に大きな影響を及ぼす可能性は否定できない」と述べているように、山岳遭難救助においては、救助者が救助時に認識し得る客観的事情の範囲(周囲の情報)は、過酷な条件下であればあるほど狭くなると考えられています。
これらのことから、困難な条件下での救助活動であればあるほど、救助者が認識し得る客観的事情の範囲(周囲の情報)は狭くなり、その分、救助者の判断には一定の不合理性が含まれてくるものといい得ます。
更に、「救助隊員の人数・身体状態・・・二次遭難に遭うおそれといった種々の事情を考慮しなければならず」と述べていることから、救助者の救助義務も救助者の一定の安全性を確保し得る範囲に限定され、要求される注意義務の水準もその範囲に限定されると裁判所も考えているものと思われます。
能力を超えた救助活動より生じた事故の法的責任
ところで、甲の主張によれば、
消防航空隊のヘリコプターは,最大全備荷重の状態でホバリングできる最高高度が3109mであり,富士山9.5合目付近での救助活動には,人員ないし装備を減らす必要があった。また,現場の酸素濃度は通常の65%で,被告救助隊員は出動からわずか30分で標高3500m付近に達しているもので,いつ高山病の症状がでてもおかしくない状況下にあった
京都地判平成29年12月7日
とのことです。
仮に、この甲の主張が正しいものだとすれば、本件事故の発生現場における救助活動は消防航空隊の救助能力を超えたものであった可能性も否定できません。
先ほど述べましたように、救助者の救助義務も救助者の一定の安全性を考慮した範囲に限定されると考えられます。
そうしますと、この事故の場合、そもそも消防航空隊に法的なAの救護義務が存在していたのかという点に疑問が生じ得ます。
この点に関しましては、上記で紹介しました別の記事で扱っている11)積丹岳遭難事故の1審判決において、
山岳救助隊員として職務を行っている警察官が遭難者を発見した場合には、適切に救助をしなければならない職務上の義務を負うというべきである
札幌地判平成24年11月19日
とされていることから、この 11)積丹岳遭難事故判決の趣旨によれば、遭難者を発見した以上、遭難者の救護義務を負うと考えられます。
そうしますと、仮に救助隊員の能力を超えた救助活動であっても、無理をして救助活動をはじめ、遭難者を発見すれば、その段階から遭難者の法的救助義務を負うと考えられることとなります。
また、仮に救助義務を否定しても、ひとたび遭難者を保護下に置いた以上、事務管理あるいは条理上の保護義務が生じるとも考えられます。
そのように考えますと、救助義務が否定されても、遭難者を保護したあとの行為に関しては、保護義務違反が認定される余地がないとは言い切れません。
そうしますと、法的な救助義務が認定される状況ではもちろん、認定されない状況においても、能力を超えた救助活動により山岳遭難者を発見し、保護下に置いた場合、遭難者保護後の行為に関し違法性が認定される余地が生じ得ることとなります。
このことから、違法性の認定を回避するためにも、遭難者保護後の救護活動についても救助隊員に能力以上の行動を求めざるを得ないことになりかねません。
12)富士山ヘリコプター事故の発生後に、甲が消防航空隊の出動対象事故の範囲を見直したのは、この点も関係しているのかもしれません。